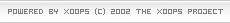| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| webadm | 投稿日時: 2020-1-2 0:49 |
Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3112 |
BWV anh. 118 B-dur Menuet 次は再びメヌエットが登場。
この曲を聞く度になぜか小学校か中学校の校歌を彷彿させます。 たぶん、カデンツの部分が学校の校歌で良く用いられるのと共通しているのかも。 故郷の小学校の校歌は確か、郷土出身の有名な作曲家によるものだというのは覚えているけど、歌詞やメロディーはすっかり忘れてしまって思い出せません。 たぶん戦後に小学校が沢山作られた時期に、校歌の作曲は郷土出身の作曲家に委託という路線が決まっていたのかも、作曲家もお金にならないけど生まれ故郷からの依頼だというのと、ずっと長く歌われるということで名誉でもあるし、低予算でも引き受けざるを得なかったと思われます。 学生時代の校歌は今も記憶に鮮明に残っていて国立だけあって、国家に果たすべき使命が歌詞に刻まれていて忘れようがありません。 学生時代に過ごした学生寮には寮歌があって、学校が提供している第一寮歌と呼ばれるものと、作曲が出来た一期生が作った第二寮歌というのがあり、記憶に残って今も歌えるのは後者の方。普通は長調なのに、第二寮歌は短調で郷里を離れて学生寮に住まうことになった若者には共感できる曲調だからかもしれません。 なんの話だったっけ? ああ、BWV and 118 ね。 このメヌエットは付点リズムが出てきます。 付点リズムは初級者の必修課題。 1拍または2泊が有理数比で3/4 と 1/4 に分割されているのを正確に再現する必要があります。更に1/4が2分割されるところもあります。 これに装飾音を入れるというとかなり感覚を研ぎ澄ます必要があります。 集中力が持たないのが悩み(´Д`;) 30分も取り組むとその後はボロボロになって再現できなくなるだけなので、昨日より良くなったかなというところで休憩を入れるのが得策。 あと、小節線を跨いで隣接する音はつなげて弾くというのもお約束。小節線はフレーズと無関係で複数拍をグループ化しているだけだから。 模範演奏動画は少ないですな。 以前に紹介したチャネルに参考になる演奏がありました。 演奏に使用している楽譜は、手持ちには無いヘンレ版のようです。 この曲もバスが朗々と歌うので、オルガン向きかも。 デジタル音源で解釈も正統派じゃないけど聞ける。 古楽器による模範演奏はないか探した。 古楽器は現代のピアノよりもっと華奢でオール有機物(木製)なので、状態が千差万別だけど正統派でいい感じ出ているよね。 個人的には鋼線ではなくガット弦の古楽器の音が好きです。 んじゃまた。 |
| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |